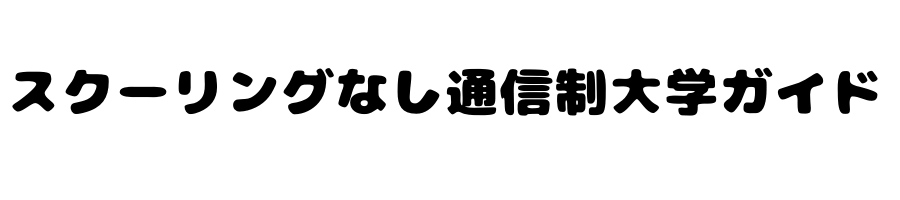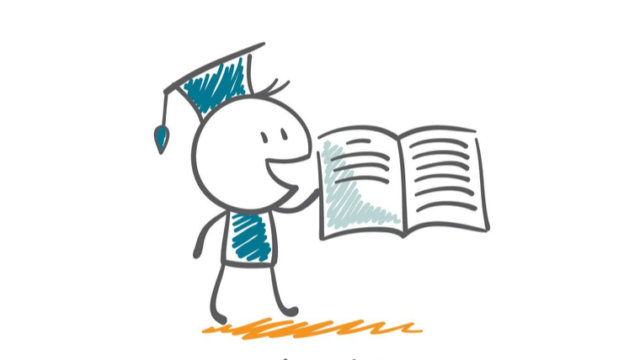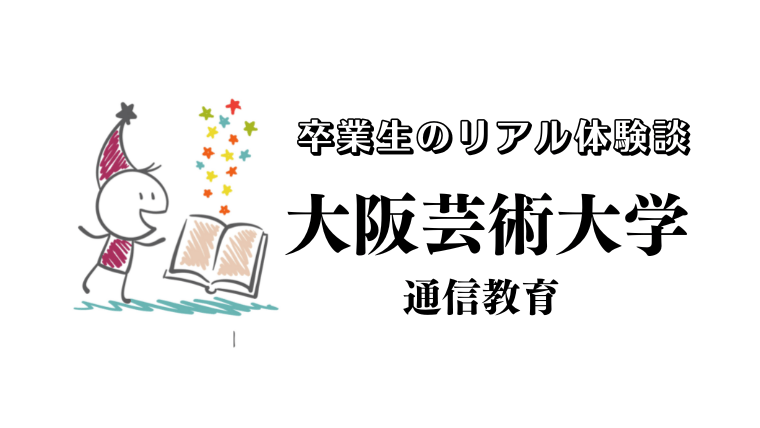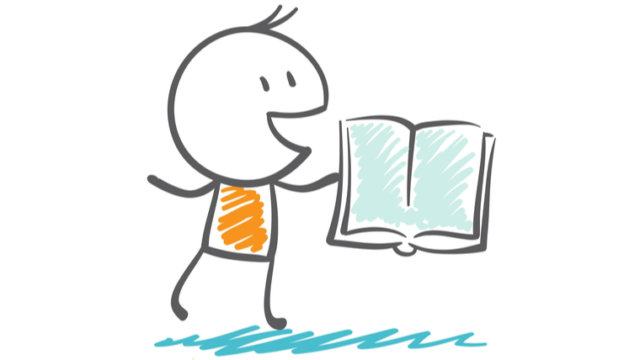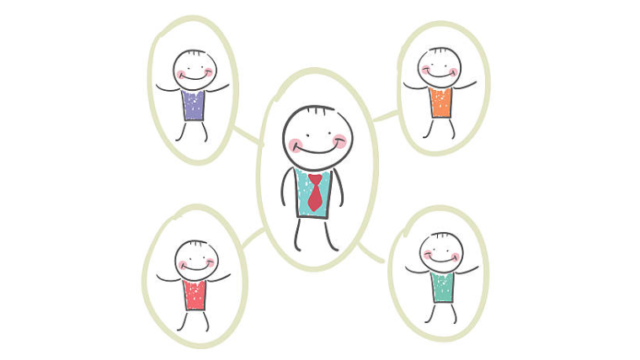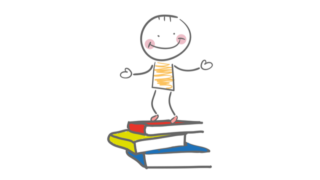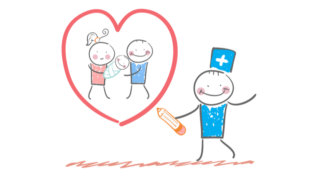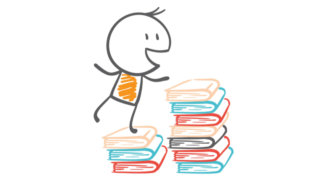目次
大阪芸術大学 通信教育部の特徴
| 大学 | 大阪芸術大学 通信教育部 |
|---|---|
| 学部 学科 | 美術学科 デザイン学科 建築学科 写真学科 文芸学科 音楽学科 初等芸術教育学科 |
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町東山469 |
| アクセス | 近鉄南大阪線・長野線「貴志駅」東駅よりスクールバス |
| 学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :10,000円 入学金 :30,000円 【年間のお支払い】 授業料 :200,000円 ※別途テキスト代、スクーリング代、資格関連費、Web教材費(音楽学科のみ) 【学費の目安】 4年間:1,260,000円 【奨学金・教育ローン】 あり |
| 入学時期 | 春期・秋期 |
| 選考方法 | 書類のみ |
| 偏差値・難易度 | 43~52(通学課程の偏差値) ※マナビジョンより引用 |
| 編入制度 | 2年生編入(一括30単位認定) 3年生編入(最大60単位認定) |
| スクーリング会場 | 大阪、東京(一部科目) |
| オンライン環境 | メディアスクーリング |
| 学習サポート | 新入生ガイダンス |
| 就職サポート | 不明 |
| 卒業率 | 非公開 |
| その他 | 一級建築士受験資格やインテリアプランナーなどの多彩な資格を目指せる |
※最新情報は資料請求するなどしてご自身で確認してくださいね。
大阪芸術大学通信教育はスクーリングなしで卒業できる
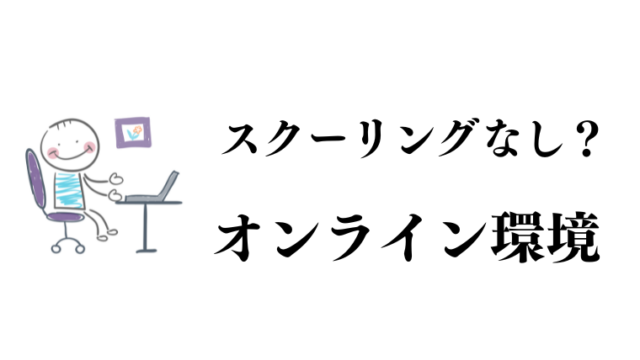
| 課題・レポート | オンライン | |
|---|---|---|
| 科目試験 | 自宅のパソコンで受ける *通学不要 | |
| スクーリング | オンライン授業 *通学不要 |
大阪芸術大学 通信教育学部 音楽科作曲コースに入学した理由
サラリーマン時代に音楽関係の会社に勤務していていました。業務は営業や販売促進などで、制作に関わることはありませんでした。
勤務しているときに、音楽の知識等がほとんどなく、音楽の知識があれば、もっと仕事にもプラスになったのに、と後悔する毎日でした。
そこで、早期退職して、時間が出来たのでゼロから音楽に関する基礎の勉強をしようと大阪芸術大学に入学いたしました。受験勉強は全くしていません。
大阪芸術大学通信のスクーリング

基本的に大学が大阪にキャンパスがあるので、そこでスクーリングを受けました。主に夏季(7~9月)と冬季(11~2月)に行われます。
夏季スクーリングはかなり科目が集中するので、1週間連続になったりすることもあるので、綿密なスケジューリングが必須で。スクーリング以外の科目はレポート提出となります。
テキストを見て作成するものや、WEBの動画を見て作成するものがあります。専門科目で結構難しいのが和声です。ⅠとⅡがあり、特にⅡは試験もあるので、しっかりと勉強しないと単位取得は難しいです。
あとソルフェージュも試験があるので、音楽教育未経験の方はある程度、別で習うなどして準備をした方がいいと思います。
勉強の進め方は、とにかく一日少しずつでも、レポート科目を進めていきながら、スクーリング科目を自分のスケジュールにうまく合わせて取得していくしかないです。
生徒の年齢は幅広く、⒑代もいれば、60代の方もいます。ほとんどの方が働きながら、勉強をしています。
私はまだ在学している音楽科は、専門スキルを問われる学科なので、通信制大学での勉強で本当に必要なスキルを学べるかどうかは、判断しかねるところです。
レポートとスクーリングで単位を取得

単位取得にはレポート提出とスクーリングの2つが必要です。さらに聴音・ソルフェージュ、和声Ⅱは試験を受けて合格しないと単位が取得出来ません。
まだ受けてないですが、結構難しく落とされる学生が多いようです。レポート提出は随時出来上がった順に提出、1200~3000字程度でインターネットや郵送で提出します。
スクーリングは夏季と冬季に集中して、参加していました。スクーリングにも宿題が出ます。スクーリング期間中は、勉強以外のことはほとんど何も出来ない状態になります。
通信教育で音大生になれた

音大の勉強を通信で出来るという点です。また、スクーリングで指導して頂ける先生がとても誠実で熱心で、どんな質問でも真剣に対応してくれたのは嬉しかったです。
一番満足している点は、スクーリングでたくさんの方に出会えたことです。ほとんどの方がアルバイトや仕事をしながら、大学に通っている方ばかりですので、色々苦労されるいることもあり、そういう方と話を出来たことはとても楽しい思い出です。
音楽関係に携わっている方も多くて、有名なスタジオミュージシャンやピアニストや、歌手の方もいました。
その方たちの音楽に対する愛情や熱意を伺うたびに、いつも感銘を受けていました。そして自分も頑張らないといけない、と励みにもなりました。
スクーリングなしで卒業できる通信制大学★一括資料請求しよう!
難しくって不合格になることも

やはり、専門科目の和声が難関でした。スクーリングは通りましたが、レポートは何回も落とされました。
通常、音大に進む場合、入学する前に受験のための勉強をするのが常識ですが、私自身、音楽の勉強を今まで全くしたことがありませんでした。
さらにピアノなど楽器を上手に弾けるわけでもないので、大学に入ってから音楽の勉強をするということになりました。
大学に入ってから、和声が難しいことが判明して、別途、音楽スクールでマンツーマンのレッスンを受けました。
通信制の大学は大学によるとは思いますが、基本高校を卒業していれば誰でも入学できます。ただ、卒業となるとかなり厳しいということを実感しました。
大阪芸術大学通信はこんな人におすすめ!
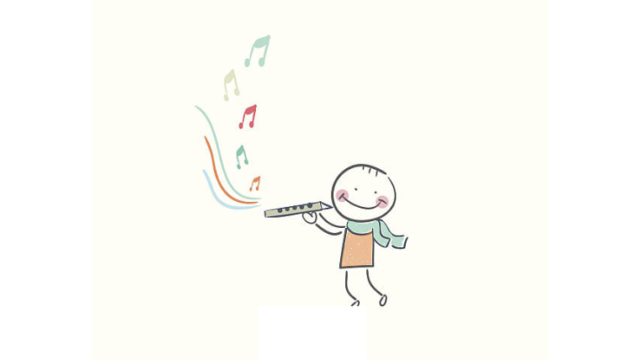
芸術系の勉強を大学の通信教育で学ぶことが出来るという点になる思います。
そして、短大を出ている方、あるいは高卒の方は、4年制の大卒の資格を持っていた方が、給与面で優遇される方(特に公立学校の先生など)は、入学をオススメします。
私の場合、全く音楽の専門知識がなく、音楽の勉強(特に作曲)を一から勉強したいという理由で入学したので、対面でマンツーマンで教えてくれる専門学校ようなところで、学習する方が良かったかな、と思ったりしましたけ。
だけど、入学しなければ、味わえない良さもありましたので、それなりに満足しています。もちろん音楽の知識がある程度あり、時間とお金の余裕のある方にも、オススメです。
卒業後の目標は作曲すること

まだ、在学中ですが、自分で満足のいく作曲が出来るようにしていきたいです。
音楽業界への就職活動というよりは、今後、自分自身で音楽活動をしていくことを考えています。自分で曲を作って誰かに歌ってもらう。
または、何か動画に自分の曲を付ける。それをSNSを通じで発表していきたいと考えています。
今現在、音楽を取り巻くビジネス環境はかなり厳しいです。仕事というよりは、趣味の一環として地道に作曲をしていき、いつかそれが世に出ることがあれば、うれしいです。
大学でたくさんの方と出会えたので、その方たちと一緒に何かコラボ出来たらなと思っています。
取得できる資格・免許

資格
教員免許
みんなの口コミ・評判
大阪芸大通信教育部のスクーリング授業⭐︎
2011年にアート作品制作を始めた頃の、ひたすら手を動かしていた時期を思い出す良い時間が過ごせました。#大阪芸大 #大阪芸術大学通信教育部 #フロッタージュ #コラージュ #美術教員免許 pic.twitter.com/OB2QXuZHg0— 宮嵜 浩 (@MiyaMiyamos) February 17, 2022

【おすすめ記事】